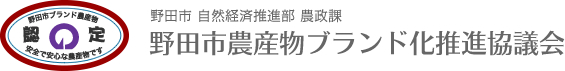野菜産地の変遷【東葛飾地域】
ア.明治以前
江戸時代初期銚子港から利根川を通り江戸に通ずる物資輸送路は、途中木下-本行徳の間を陸路により、大森・白井・鎌ヶ谷・八幡を経由した。利根川河道の整備と江戸川の改修によって舟運が開かれこの方が漸次重要度を増した。木下と本行徳間は馬による荷駄で、舟運に交替する過程が見られる。正徳6年(1716)「布佐・松戸・江戸の舟路開発され、陸路の駄送次第に衰え」村々から幕府に請願が出されている。
江戸の人口増加と共に、近在農村における野菜の生産が拡大した。江戸の西部の台地地帯と東部の島畑地帯に、両者平行して産地が伸びたが、東部の産地は足立・南葛飾から、東葛飾へと広がった。その広がり方の一つは陸路を八幡・鎌ヶ谷方面へ向かうものであり、他の一つは水路を市川・松戸方面へ向うものである。
江戸末期において、これらの産地と江戸の間の経路は東葛飾の西部に於て錯綜し、山中・舩橋から舟運が、市川・松戸から駄送がなされている。
生産する野菜の種類は、近在産地のものが産地を広げたものであるが、それらは東葛飾の産地で、既に自家用に作られてきたものが多い。それらは殆んど導入の記録を欠くが、特定のものでは伝承がある。
享和元年(1801)八柱村大橋の花沢長左衛門がみつばを水元村(現東京都葛飾区)から導入して栽培を始め、文化年間(1804~)八柱村和名ヶ谷の浮谷孫右衛門がみつばを千住に出荷している等は、近在産地が島畑地帯から台地地帯へと拡大したことを物語る。
千住への出荷は駄送と人肩でなされた。市川で享和3年(1803)「瓜・西瓜・大根・茄子等を作り、行徳河岸を通じて江戸に販売した」のは、舟運によるものである。
東葛飾の野菜生産は享保年間に、江戸における需要増加に対応して、生産が急増したようである。市川では「この頃江戸の野菜需要増加し、近在農民はこれに応えるために下肥によって生産力を挙げようとした」とあり、下肥の利用が当地域の野菜生産と密接に結びついて展開した。
元禄から宝永の頃まで江戸近在の農家は住民の下肥を無料で汲み取っていたが、以後有料となり購入に変わった。下肥販売権は大家・家主が持ち、現物を商人に売り、商人は買取った下肥を近郊農村に販売した。船によるものを「葛西船」と呼んだ。
下肥売買に対して幕府は監視をしており、寛政4年(1792)幕府は、「葛西船」に対して下肥の値下げを命じている。野菜栽培における下肥の利用が次第に広範囲に及んだことは、例えば東葛飾では天保9年(1838)「柏井村の百姓は瓜・西瓜・芋・大根を作り江戸に売り、肥料は下肥船(葛西船)に頼ることになる」によって知ることができる。
また13年「売品として里芋・瓜・西瓜の名出づ、取引は堀江村・中山村・鬼越村等近郊にとどまらず、浅草・本所等へも舟出している。
代りに厩肥・干鰯・油粕等を購入した」とあり、近在野菜産地の成立を示している。
下肥購入の範囲が広がり、農家と業者との間に紛議が生じたため、弘化3年「幕府は勘定奉行支配下の役人が中に入り、下肥の値段を定めた。関係範囲は八条・二合半・平柳・矢古田・渕江・西葛西・東葛西・行徳の諸領に及んだ」とあり、東葛飾がその圏域となっていることを示している。
松戸下矢切の渋谷熊次がねぎ種子を南葛飾郡金町村柴又の島崎某から入手して栽培を始めたのが嘉永5年(1852)で、柴又は江戸川を挟んで下矢切の対岸の地である。
品種は「千住葱」で、金町村は既にねぎの産地化が進んでいたところである。また、江戸末期まで東葛飾郡のみつばは殆んど冬季軟化栽培であり粗放な根みつば栽培ではなく、集約的な野菜栽培も施行的に進んでいた。
イ.明治・大正時代
東葛飾の野菜生産にとって、明治時代というのは、資本主義経済のもとで、東京における野菜需要の増加に対応して、大いに産地化が進んだ時代である。野菜の種類と数量が多くなっただけでなく、同種類でも新しい品種の導入に努め、栽培方法に温床栽培を取り入れて出荷時期を広げ、輪作の導入によって、生産・出荷と土地利用の集約化・合理化を進める努力がなされた。
明治初年に既に量的生産が進んでいたが、かんしょ・さといも・だいこん・にんじん・ごぼう・なす・しろうり・きゅうり・かぼちゃなどが漸増するなかで、ねぎ・すいか・まくわうり・しょうが・みつばなどが需給増加のもとで、流行的に生産が増加している。明治初年に本郷で急増したのはみつばであり、八柱を中心に高木・鎌ヶ谷で栽培が増加し、東京市場及び地元商人に販売され、その産地が永続するのである。
明治20年代後半を境として、本地域の野菜生産が大きく伸びるのは、日清戦争を契機として東京の人口増加が進み需要が増加したことに加え、明治29年(1896)に常磐線が開通したことが松戸地方の野菜作を急伸させ、また、27年の総武線の開通が東葛飾南部地域の野菜栽培を増加させた。また地元消費でも市川の野戦重砲連隊、習志野の騎兵旅団の設置が、大きく貢献して産地形成が進んだ。30年に東葛飾地域から県外に移出された野菜としては、かんしょが116万7,000貫で5万77円、その他野菜が23万3,504貫、6,582円で主として東京方面へ出荷された。
(ア) きゅうり
きゅうりは、明治30年(1897)に作付面積28.6㌶、収穫量2万7,170貫、生産額951円とある。なすと比較してかなり少ない。大正8年(1919)には作付面積67.4㌶、収穫量1,088㌧、生産額40万9,988円と伸展が著しい。特にその反収が明治30年(1897)95貫、大正8年431貫と増加している。明治時代には地ばい種で、防除技術が遅れていたが、大正時代に入ると節成種(三枚目・馬込等)が作られ、支柱仕立てに変わった。これはボルドー液が普及したためである。10a当たり収益増加とともに、作柄が安定した。
大正時代の主産地は松戸・塚田・行徳などである。
(イ) すいか
東葛飾のすいか栽培は前記の如く江戸時代になされた記録があり、明治30年(1897)には59㌶の作付があった。収穫量554㌧、生産額4,440円とある。それが大正2年(1913)には作付面積35㌶、収穫量619㌧、生産額2万1,785円であるから、生産は停滞している。大正前期の主要産地は船橋・鎌ヶ谷・法典・塚田・八柱・高木等で、中でも船橋町附近に産するものを船橋西瓜と呼び、市場で定評があった。広く栽培された品種は、「アイスクリーム」、「マウンテンスウヰート」等の輸入種と、「黒皮」と称する在来種であった。この時期に栽培はかなり増加して、大正8年(1919)には、作付面積75.3㌶、収穫量1,290㌧、生産額7万9,056円となった。しかし、全般的に本郷のすいかは市場に於て不評であった。即ち「本郷の西瓜形状不良甘味乏しいとの悪評広まる」で他産地と競争して早取りし、早期出荷をしたためである。そこで、「育苗法を改良して10日から15日間出荷を早める研究が必要」視されるに至った。
(ウ) かぼちゃ
かぼちゃも江戸時代から作られ、明治時代には主要野菜の一つとして数えられるに至った。明治30年(1897)の作付面積61.9㌶、収穫量464㌧、生産額6,190円。44年の主要産地は松戸・明である。大正8年(1919)には作付面積106㌶、収穫量1,908㌧、生産額7万2,293円と増加している。特に反収及び単価の伸びが大きい。主産地も松戸・塚田・鎌ヶ谷・明・手賀・八栄等で、主な品種は「菊座」、「ちりめん」である。
(エ) まくわうり
本地域のまくわうりの栽培は古く、江戸川対岸の水元(現葛飾区)から入ったと考えられる。明治30年(1897)の作付面積84.6㌶、収穫量1,140㌧、生産額1万6,750円とかなりの生産が行われている。明治末に生産が増加したが、大正期に入り減少し、大正8年(1919)には作付面積68.7㌶、収穫量964㌧、生産額53万959円となり、大正末期にかけて漸減した。主産地は八柱・塚田・法田・八栄・松戸。主要品種は「梨瓜」・「銀甜瓜」・「金甜瓜」等である。
(オ) しろうり
しろうりの種類を2大別して、白瓜と越瓜に分ける。白瓜は白色で一夜漬け若しくは生食用であり、越瓜は青瓜・つけうりともいい、糠漬けや普通の漬物にする。明治30年(1897)には、統計に白瓜のみが記載され、作付面積60.4㌶、収穫量351㌧、生産額3,744円とある。作付面積は数10㌶で推移し、大正5年(1916)の39.1㌶で終っている。これに対して越瓜は明治42年(1909)初めて統計に記載され、大正5年(1916)まで数㌶の面積で推移している。6年から白瓜の面積を合わせて越瓜とし、47.9㌶となるが、大正14年に47.0㌶とその面積は停滞している。本地域では白瓜に代って越瓜が漬瓜の大産地として成立したところではないが、小産地で、白瓜が越瓜に替るという変化があったことが考えられる。
(カ) トマト
本地域のトマトが最初に統計に現れるのは明治44年(1911)で0.4㌶、同年の全県が0.5㌶であるから、この時期に本県に導入が始まったと考えられる。それが大正14年に東葛飾で0.6㌶、全県で7.8㌶と、生産はまだ僅かである。
(キ) なす
なすは本地域における果菜類の生産の中で、明治・大正時代を通じて第1位を占めた。明治30年(1891)の作付面積76.8町歩、収穫量187㌧、生産額2,496円で、大正8年(1919)には112.9㌶、1,004㌧、7万1,871円となり、大正14年(1925)には196㌶となった。大正時代になってから作付の増加が見られる。大正時代の主産地は松戸・野田・我孫子・船橋・千代田・木間ケ瀬等で、品種は「真黒」・「千成」・「山茄」等である。
(ク) いちご
市川新田の後藤弥五右衛門が、「ドクトル・モーレル」種を導入、栽培を始めたのが明治35年(1902)で当地における最初の栽培である。本種は早生種で果実が大きく、1個14~15匁に達し濃赤色で、果心に空洞を生ずる欠点があったが、福羽逸人は「其強剛にして豊産なる其香味良形状偉大なるとを以って普く各地に栽培する者あるに至れり」と書いている。次いで同地で、明治41年大柏姥山から早生種「ビクトリア」を導入、栽培し東京市場に出荷して好成績を収めた。これが市川各地に普及した。明治43年晩生の「クラークシードリンク」を導入、出荷時期の延長に効果があった。大正2年(1913)には、市川新田のみならず、同町の島畑地帯に晩生種「クラーク」の栽培が増加、砂質地帯に「ビクトリア」の栽培が広がって、栽培面積は数㌶に達した。4年には千葉県農試の大島亨が、「大島苺」「千葉1号」等の品種を育成している。市川のいちご産地でこれを導入、大正末期に至り「大島苺」が東京市場で高い評価を受けた。市川におけるいちごの栽培面積は約20㌶、全県の80%を占めるに至った。しかし、関東大震災後、市川の砂質地帯が罹災者の居住地となり、いちご栽培地が圧迫され、生産について検討が加えられることになった。いちご産地が台地地帯に広がるのは戦後のことで、当時は島畑地帯及び砂質地帯に適地を求めて拡大した。
(ケ) いんげん(未成熟)
東京東部の南葛飾に作付された、いんげんは、有蔓種の「ソーヅル」「白実」等で、「ソーヅル」は「群房」とも呼ばれ小莢で収穫に多くの労力を要した。有蔓種の「地種」「白実」「黒実」もあったが、収穫物が不揃いで内方に弯曲しやすかった。明治末期に東京のやまと種苗がアメリカから「ケンタッキーワンダー」を輸入して試みたが南葛飾には普及せず、大正初年になってこれが東葛飾と印旛に普及した。「どじょういんげん」という呼び名はその頃付けられた。大正4年(1915)に初めて統計に記載され、東葛飾は18.7㌶とある。その後、大正8年に22.8㌶、大正10年には39.4㌶となった。本品種は大莢で収量が多く、大衆向け需要の増加とともに本地域における生産も増加した。
(コ) はくさい
明治末期に本郡地域の農家に栽培が試みられた結球はくさいは、その成績が良好であったために漸次普及した。明治39年(1906)1月千葉県農友会主催の大回重要農産物品評会で、本地域からはくさいを出品して受賞した者の中に、福田村風見市郎右衛門の名が見られる。東葛飾郡農会は大いにこれを奨励し、結球はくさいの栽培が盛んになった。品種は「芝罘」「直隷」等で、産地は野田・福田・田中等で、つけなの産地と同様である。栽培面積は大正2年(1913)が12.3㌶で、大正時代後半にかけて急速に普及した。
(サ) キャベツ
本地域のキャベツは、明治・大正時代は導入の時代である。本県の統計に初めて現れるのは明治38年(1905)で、全県の作付面積が1.5㌶、東葛飾は明治43年に0.2㌶が初めて作られた。それが大正8年(1919)に3.2㌶、大正14年には9.5㌶となった。
(シ) つけな・こまつな
本地域における菜類は明治時代にはつけなが作られた。いわゆる非結球つけな類で、三河島菜・杓子菜・山東菜等である。作付面積は明治42年(1909)が97.9㌶、大正8年(1919)が123.7㌶である。他にこまつな・芥菜等があるが僅かでこまつなは明治42年(1909)に4.7㌶である。大正時代の菜類の主産地は、野田・福田・田中・手賀・風早等である。
(ス) ほうれん草
ほうれん草は江戸川対岸の南葛飾で明治43年(1910)作付面積3.0㌶とあり、大正元年(1912)には郡農会から耕種および収支が示され、大正3年には作付面積が15.6㌶になった。大正5年の主な産地は砂村で、同年今後作付を増す野菜の一つに数えられ、大正13年には全町村に普及した。このことからすると、東葛飾でもその導入と作付の増加はそれほどの違いがなく行われたと考えられる。東葛飾では昭和2年に作付が22.4㌶であるから、近郊産地という意味でその経過を対比できよう。
(セ) ねぎ
嘉永年間江戸川対岸の金町から入った「千住葱」は普及しなかったが、明治20年(1887)同じく下矢切の渋谷仁助が、南葛飾郡砂村から導入したねぎは品種が赤柄で、これを栽培したのが普及の端緒となった。「千住葱」は一般に根深葱と称せられ、赤柄・黒柄・合柄の3種がある。次いで下矢切の高安金次郎が赤柄種を砂村から導入栽培、明治35年下矢切に砂村から合柄種が導入栽培されている。明治末に松戸近傍にねぎの栽培広まり、品種は赤柄・黒柄・合柄の何れもが栽培されている。本地域におけるねぎの栽培面積の増加は特に顕著で、東葛飾全域で明治30年(1897)に僅かに37㌶であったのが、明治45年、213㌶、大正9年(1920)315㌶と増加した。その主要産地は明治44年に松戸・八柱・明・馬橋・小金・高木・国分・八栄・船橋に広がり、東京市場への大きな産地となった。
(ソ) らっきょう
本県のらっきょうの作付面積が県統計に初めて現れるのは明治39年(1906)で、全県で1.5㌶とある。同年東葛飾はゼロであったが、2年後の明治41年には21.3㌶で、全県99.4㌶の21%を占め、その後軍需との結びつきもあって作付を増加し、大正8年(1919)には275.5㌶で、全県532.5㌶の51.7%を占め、収穫量2,587㌧、生産額13万5,642円と県下一の産地となった。また、大正14年には435.0㌶で全県643.0㌶の67.7%に達する。主産地は千代田・田中・富勢・我孫子・高木等である。この地方は宅地内の空地、山畑等を利用して比較的収量があり、農家経済に収入をもたらすことから、作付が急増した。
(タ) みつば
みつばは軟化みつばであり、明治時代に新産地が登場する。明治初年八柱を中心に高木・鎌ヶ谷等に増加し、東京市場・地元商人に販売している。八柱は江戸時代から当地域における軟化みつばの発祥地である。この附近を中心にして栽培地域が広がり、明治44年(1911)の主産地は松戸・八柱・明・馬橋・小金・高木・松戸となった。軟化みつばには根株の養成を伴なう。その面積は、明治42年(1909)35㌶、大正4年(1915)156㌶、大正14年(1925)451㌶と地域全体に広がった。東葛飾における軟化促成の唯一のものであった。作型は冬季促成軟化が最も多く行われた。
(チ) だいこん
だいこんも古くから作られ、江戸時代にもその記録を見ることができる。明治23年(1890)に883㌶が作られたが、30年には302㌶と減少した。その後は栽培が順調に推移して明治44年(1911)739㌶、大正14年(1925)には660㌶となった。多くの野菜が栽培を増加した中で、変動の少ない例である。主産地は船橋・八栄・鎌ヶ谷・高木・塚・国分・法典等であり、品種は「徳利」・「秋詰り」・「二年子」・「春大根」・「美濃早生」・「亀戸」等である。切干用・煮食・漬物用に大別され、明治20年(1887)頃、大根切干が鎌ヶ谷村で盛んにつくられたが、大正時代になり愛知・宮崎等の産地に押されて減少した。「徳利大根」を使用したために、愛知・宮崎県産よりも低価格であったためである。産地は鎌ヶ谷・道野辺・初富等で、減少したといっても大正12年(1923)に収穫量6万1,000貫、生産額3万余円をあげている。
(ツ) こかぶ
本地域のこかぶは明治末期に導入され栽培が始まった。明治42年(1909)の作付面積が1.1㌶で、全県では73.1㌶当時印旛・山武に早く導入された。本地域では大正8年(1919)作付8.8㌶、大正14年(1925)14.8㌶でまだ産地形成は未熟である。後にこかぶの大産地となった豊四季(現柏市は昭和8年(1933)に150㌶)では、大正中期(大正7年頃)に東京府下金町地方から導入され、下谷区上野の福神漬業者の依託栽培として増加した。6年に東京東部に台風による水害があり、産地が徐々に東葛飾へ移動したものである。
(テ) にんじん
江戸時代から栽培が行われ、根菜類中主要なものの一つである。明治30年(1897)の作付面積39.7㌶、収穫量470㌧、生産額2,761円、大正8年(1919)の作付面積59.3㌶、収穫量12万8,165貫、生産額3万460円で、生産の伸びは大きくない。主産地は手賀・松戸・風早等。主な品種は「金時」「滝野川」「三寸」等である。
(ト) かんしょ
東葛飾のかんしょ生産は古くから行われ、かつ、その規模も大きい。明治20年(1887)が1,095㌶、30年には1,230㌶、収穫量11,610㌧、生産額15万5,000円で、野菜類作付中第1位を占めている。
(ナ) ごぼう
だいこんに次ぐ作付面積をもち、明治30年(1897)に作付面積50.5㌶、収穫量817㌧、生産額1万3,089円であるが、その増加は緩慢で数10㌶で推移し、大正8年(1919)が78.6㌶、900㌧、4万5,520円で、100㌶を超えたのは10年である。主産地は八栄・鎌ヶ谷・松戸・湖北・手賀で品種は「瀧ノ川」・「砂川」・「梅田」等である。
(ニ) さといも
江戸時代にさといもの名が当地方の野菜の中に見られ、明治時代にも主要な野菜として存続する。青芋ともいわれ、明治30年(1897)の作付面積216㌶、収穫量1,618㌧、生産額1万7,280円であった。36年には作付302㌶、県全体で1,078㌶であるからその28%強は東葛飾郡である。大正8年(1919)には作付面積480㌶、収穫量4,322㌧、生産額42万円で20年間に面積が2.2倍、収穫量が2.7倍、生産額が25倍になった。主産地は鎌ヶ谷・川間・高木・田中・旭・木間ケ瀬等で、主要品種は「赤芽」・「八ッ頭」・「早生馬鹿」などであった。
(ヌ) しょうが
古くから川間・手賀・福田地区で作られたが、明治30年頃手賀村須藤覚之助がしょうが栽培の利益のあることを紹介し、栽培が広がった。同年の本地域におけるしょうがは、作付面積6.8㌶、収穫量20㌧、生産額679年であるが、大正8年には32.8㌶、322㌧、3万4,242円になった。品種は「芽根」・「当尾」である。
(ネ) れんこん
東葛飾のれんこん作付が県統計に最初に登場するのは明治36年(1903)で5.4㌶作られている。これが漸増して明治44年に15.2㌶、大正8年(1919)に55.0㌶、大正14年には68.8㌶となった。
湿田で表土の深い土地に作られ、下肥・魚粕等を肥料とした。在来種のうち「天王種」が多く、これは、腐敗病に弱く収量が少ないが、大正8年(1919)にも主な品種として記載されている。同年の生産額7万8,901円で、主産地は行徳・葛飾・八幡・市川・明等である。
(ノ) 下肥
本地域の野菜生産の発展は、進んだ栽培技術と、消費地に近接する恵まれた立地条件によるが、さらに廉価多量に得られる下肥によって、生産物の増収に努力を払ってきたことにもよる。野菜産地の広がりと、東京を主とした都市の下肥の利用とは密接に関連している。
明治末には江戸川の運輸を利用して浦安から関宿までの町村に、東京市の人糞尿が購入使用されている。農家が船を用いて購入するのではなく、業者が船で運び貯溜してあるものを農家が購入して使用するのが普通であった。いわゆる下肥肥料問屋である。
大正5年(1916)の調査によれば、松戸町の江戸川畔に肥料問屋が経営する人糞尿・牛糞・馬糞・廏肥・その他有機質肥料の貯蔵所があった。問屋仲間5人の集合貯蔵地で、面積1町5、6反、仕入先は人糞尿は両国辺、牛糞は本所、馬糞は竹橋の宮内省内、市ヶ谷の士官学校等である。
江戸川・中川の水利を利用して運び入る。通称12石船と呼ぶ船で人糞尿は12石、牛糞・馬糞は4,000貫、これを一度に3~4艘搬入する。問屋の肥溜は牛馬糞の堆積所と同一地にあり、需要者の汲取りに便利なように、道路の左右に設置されている。雨露を凌ぐ屋根はあるが、肥溜の蓋はない。杉板で直径4~6尺で6石入というのが多く、これを地中に埋設して上部を4~8寸地上に出してある。
1カ月平均120艘の人糞尿が入荷するので、百数十の溜が並んでいる。比較的安価で品質優良の野菜を生産できるというので、松戸・馬橋・明・八柱・大板等の農家がこれを利用した。このような肥料問屋による江戸川筋の下肥販売所は他にもあったと考えられる。価格は大正5年(1916)の時期で1艘分人糞尿4円50銭乃至6円50銭、牛糞20円、馬糞40円である。一般農家は肥溜を造り購入貯蔵することなく、必要に応じ5荷、10荷(1荷は20貫)と購入し直ちに施用する状態であった。牛糞・馬糞についても同様で、堆積貯蔵する小屋を持たず、必要に応じて購入施用した。この改良指導に着手するのは昭和期に入ってからである。
ウ.昭和戦前時代
都市近郊の野菜産地として、本地域は昭和戦前時代に発展をとげ、県下最大の産地に成長した。その野菜作面積と全県のそれに対する割合を示すと、大正2年(1913)2,370㌶、23%、大正6年3,415㌶、28%、昭和15年(1940)5,704㌶、32%(いづれもいも類を除く)となる。
この間に、新しい野菜の種類が増加したのではなくて、新産地の形成と、新品種及び新栽培法が実現した。また種子の生産と販売が個人及び販売組織の下に拡大した。
昭和15年(1940)における作付面積をいも類を含めて多い順に挙げると、かんしょ2,225㌶、さといも1,088㌶、ねぎ979㌶、だいこん905㌶、ばれいしょ876㌶、つけな(はくさいを含む)710㌶、ほうれん草432㌶、すいか359㌶、しょうが352㌶、きゅうり339㌶、みつば324㌶、なす250㌶、らっきょう241㌶、こかぶ220㌶で、この14品目で野菜作面積の90%を占める。
全県では85%である。全県の栽培面積に対してねぎ52.4%、みつば84.6%、こかぶ57.6%、しょうが64.5%などが比率が高く、技術水準も高く、近郊の立地条件を生かした品目といえる。昭和7年(1932)塚田村高橋広は割竹とパラフィン被覆により、すいかの一番果を7月12日から収穫し、昭和10年(1935)松戸町渡辺農園は「都1号」その他各種のすいか種子を販売し、これが昭和10年代の普及に一役買っている。
当時この地方にすいか・トマトの栽培が多くなり、夜間の畑荒しが横行したため、生産者が夜警をするところもあった。昭和初年市川町を中心とした苺生産は進展しつつあったが、昭和6年(1931)、市川町で促成用の「福羽苺」を導入したのを契機に「市川新田苺生産組合」が結成せられ、電熱促成栽培を取り入れ、共同選果、共同出荷、包装の改良を行った。この頃から市川いちごは全盛時代を迎えた。
現在の野菜産地
ア なす(暖房設備を持たない関宿のなす)
1.産地のおいたちとあらまし関宿町のなすは、木間ケ瀬地区で昭和の初期(昭和5年(1930)木間ケ瀬村史)に2.7㌶作られていたと云われるが、産地として知られるようになったのは、昭和42年(1967)以降である。
半促成は、42年の秋から木間ケ瀬地区の前村出荷組合6人がパイプハウス(50a)を利用して栽培したのが始まりである。
その後44年(1969)3月12日、千葉県北部を襲った未曽有の大雪でハウスは倒壊し、なすにも大きな被害を与えた。ハウス被害面積は8万㎡にのぼった。トマト・きゅうりは全然回復せず、収穫は皆無となったが、なすは更新剪定を行い、5月には回復して出荷ができた。
その年は価格にも恵まれたこともあり、その後面積は年々増加し、56年(1981)には14㌶で、県下でも半促成産地としては最も大きな産地となった。
なすの半促成栽培は前村・武者土・高倉に多く、殆んどが専業農家である。1戸当り10a以上で、多い人でも20a程度である。
この他、40年(1965)20ha近くあった露地なすも、42年頃から、2・4-Dによるホルモン処理技術の普及で、着果が安定したので、トンネル栽培に移行し、56年(1981)にはトンネル栽培が40㌶・露地栽培は秋の抑制栽培が主で約5㌶となり関宿町の特産野菜となった。45~47年野菜新興産地育成事業による集出荷用建物が造られ、なす及びいんげんの共同出荷がなされている。
2.技術と経営の特色(半促成栽培)
| 施設 | 間口4.5mのパイプ連棟ハウス |
|---|---|
| 育苗 | 接ぎ木育苗(割接) |
| 品種 | 台木「VF」「赤なす」穂「金井改良早真」 |
| 栽植距離 | 1ハウス2ベット 1ベット2条植 株間55~60cm |
| 保温処理 | マルチ+小型トンネル、小型トンネル除去後二重カーテン、暖房施設は少ない |
| ホルモン | 単花処理 2・4-Dアミン塩2~4万倍液、全面処理 2・4-Dアミン塩20~50万倍液、草勢により濃度、散布量を変える。 |
| 誘引 | 3本仕立、テープで適宜誘引 |
| 収穫 | 暖房設備を持たないので、収穫始めは3月上旬だが、収穫最盛期が4~5月になるような管理をしている。収穫終りは、後作の関係で7月中・下旬。 |
| 後作 | きゅうりが主体だが、最近夏ほうれん草の農家が増加している。 |
ア えだまめ(兼業農家も専業農家なみ野田市のえだまめ)
1.産地のおいたちとあらまし
野田市のえだまめの栽培面積は約300㌶と云われる程多い。野田市での栽培は昭和20年代の後半からで、当時は、多くの農家が、自家用の味噌作りなどのために大豆を作っていた。
20年代の後半になると食糧事情も徐々に回復してきたので、大豆からえだまめへと転換した。
市内には、種苗業者の委託で「西新井」「三河島」等のえだまめ用の採取をしていたので、これらの品種を使って、野田市の旭地区でえだまめを栽培する農家が出てきた。
組合単位で組織的な栽培、出荷をしたのは、32年(1957)に野田市の目吹出荷組合で、その後、旭地区を中心に市内全域に広がった。当時は、直播で4月上~中旬蒔きで7月下旬から8月上旬収穫が大部分であった。
「奥原一号」を使って移植栽培を行い早出し栽培が試みられたのは40年(1965)で、43年(1968)にはマルチ栽培も行われるようになった。
出荷組合単位で共販共計の実施を指導しているが、なかなか進まないのが現状である。現在は○谷出荷組合と旭出荷組合が実施し成果を上げている。
野田市のえだまめは、兼業農家も専業農家に負けない程の力を発揮していることが特徴である。
2.技術と経営の特色
野田市のえだまめ栽培は、秋から春がほうれん草、夏の高温時にはえだまめと比較的無理のない輪作体系である。
また、兼用農家が85㌫以上と多いので、果菜類等のような高度な技術を要するものは不向きで、この点、えだまめとほうれん草の輪作は技術的にも経営的にも野田市には適している。
現在、野田市のえだまめ栽培の作型は
①トンネル+マルチ、②トンネル栽培、③マルチ栽培、④露地栽培の4つの作型で栽培されている。
何れも殆んど移植栽培が行われている。
この移植栽培は前作が、ほうれん草などの葉物を栽培するために畑が肥沃で、えだまめの徒長や過繁茂を防ぐのに役立っている。
品種は、6月出しに「奥原早生」「白鳥」が多く、7月出しは「洞爺」「サッポロミドリ」「ユキムスメ」等最近数多くの品種がとり入れられている。
播種は、3月上旬から順次行い育苗期間は20日前後である。最終の播種は6月上旬で、8月に入ってのえだまめはサヤタマバエなどの被害で品質が落ちるので、7月迄を出荷の目標にしている。
組織販売で出発した関宿町のいんげん
1.産地のおいたちとあらまし
いんげんは病害虫がトマト・きゅうりに比べて少なく、また夏果菜類のように育苗も難しくない。このため経験の少ない人でも作り易い。
関宿町におけるいんげんの産地化の最初の原動力は、昭和26年(1951)に前村出荷組合が組合としていんげん栽培を試み、28年(1953)から本格的に組合出荷を行ったことから始まる。
当時としては共同出荷は珍しく規格の統一、売上金のプール計算と進んだ販売方法の実施によって一躍市場の人気を呼び、有利な販売ができた。
このことから、町内各地域に拡がり、30年代後半からは、ビニールトンネルの普及などにより、収穫期間が延長し収量も増加し収量・価格共に安定し、昭和40年(1965)には100㌶を超す大型産地となった。
地域的には、昭和30年代は木間ケ瀬地区が主体に栽培されたが、40年代に入り、たばこが急激に減り、これに代わって二川地区へと移行した。現在では面積・生産量共に二川地区の方が多い。
近年、いんげんも他産地の出現や、宅地化さらに労働力の減少等から年々減少傾向にあり、昭和56年(1981)には30㌶程度に減った。
しかし、関宿町の野菜としては今なお、重要な地位を占めている。
これからの産地の動向としては宅地化のみでなく資材・労力・品質等の点からみて当地のいんげんは今日以上の産地拡大は望めない。
作型としては、トンネルが主体で一部パイプハウスを利用して早期化が図られている。
昭和45~47年野菜新興産地育成事業が県によって実施されている。
2.技術と経営の特色
品種は「黒種ケンタッキー」を用いているが、関宿町では「黒種」と称して作られ、一般の「ケンタッキー」よりも品質的には劣る。市場からは品質の点で指摘されているが、早生種で雨や低温等の不良環境でも着莢しやすいので、この「黒種」を殆んどの農家が作っている。
育苗の早いものは、ビニールハウス内に踏込温床を作り、そこに練床を作る。また、冷床で練床育苗もする。ブロックは10cm角程度が多い。
種まきは、3月上旬から順次行い、育苗日数は30~40日のものを使う。
経営近郊のために、いんげん栽培農家でもトマト・なす・春白菜など数種類の野菜を作る。このために、他の野菜との関係で面積・作期を調整している。面積は1戸5a程度で、多い農家でも20a程度である。
はくさい(葉茎菜類)資材の効率的な活用で伸びた関宿町の春はくさい
1.産地のおいたちとあらまし
関宿町の秋冬結球はくさい栽培の歴史は古く、東葛飾郡誌によれば、大正10年頃すでに木間ケ瀬地区に結球はくさい栽培の記録がある
(「木間ケ瀬村誌」大正15年(1926)9.2㌶、昭和5年(1930)18.4㌶、10年(1935)46.3㌶)。
戦前にも、すいかの後作として、はくさいを作付し江戸川の人糞運搬船を利用して市場に出荷したと云われる。
本格的に産地化したのは昭和25年頃より練床育苗の技術が普及した頃といわれる。
たばこの後作にはくさいが導入されるようになり急激に増加し、野田、関宿で30年(1955)には約300㌶と云われた。
30年代後半になり、モザイク病や軟腐病などで作柄が不安定になり、夏みの早生大根へと転換し、現在では秋のはくさいは自家用程度となっている。
現在、関宿町のはくさいは、春はくさいが主体で、木間ケ瀬・二川地区の全域に栽培されている。昭和45年(1970)に岡田地区の石山利久が茨城県の金岡から導入したといわれその面積は56年(1981)で約20㌶である。
岡田地区はトマトのトンネル栽培が多く、この資材を効率よく利用するために導入された。
更に、昭和48年(1973)4月に春はくさいの価格が1ケース2,800円という暴騰により、地域の関心が深まり、年々面積は広がり、今日に至っている。
トンネル栽培の多い関宿町では資材の有効利用の面で、有望な野菜のために伸びる可能性を持つ野菜の一つといえる。
2.技術と経営の特色
作型 トマト・いんげんなどの被覆資材を活用しての春はくさいの栽培である。12月下旬温床は播種し、1月上中旬にポット移植をし、2月上中旬に植え付け3月下旬には、トンネルを除去する。そして夏果菜の定植直後の4月中旬から出荷すると労力の配分も良い。
| 品種 | トンネル栽培 「クリーム」「さくら」「50日」(長交)。無被覆栽培「無双」。 |
|---|---|
| 育苗 | パイプハウス内に踏込温床を作り播種 |
| 移植床 | 連結ポット(16ケ)に練った土を流し込み、 ここに移植する(本葉の出始)。育苗日数30~40日。 |
| 定植期 | 2月中旬から定植するが、厳寒期にはコモの被覆をする。 植付けは、マルチ(1.3m幅・3条・株間42㎝)を敷き、 温暖な日を選び植え付け密閉して保温に努める。 |
| 管理 | 活着して伸び始めるまで密閉して、以後日中暖かい日は換気する。 換気不十分で軟弱に過ぎると寒害を受けやすい。 トンネル除去は、3月中下旬、静かな暖かい日を選ぶ。 この資材は後作のトマト・いんげんのトンネル栽培に利用する。 |
キャベツ(葉茎菜類)共販共計で伸びた関宿町のキャベツ
1.産地のおいたちとあらまし
関宿町で組合としてキャベツを導入したのは二川地区の○平出荷組合が古く、昭和28年(1953)当時の当地方の秋野菜ははくさい全盛時代だった。
○平組合の人数が豊島青果で都下産のキャベツを見て、はくさいだけではなくキャベツはどうかと云うことで「川崎甘藍」の10月出しを試験栽培し33年(1958)から出荷組合を行い徐々に他地域へも広まった。
しかし、本格的に二川、木間ケ瀬地域に広まったのは、48年(1973)から実施した東京都との契約栽培からである。関宿町の両地域全域にキャベツが広まった経過は長く迂余曲節がある。
昭和20年代から30年代前半ははくさいの全盛時代であるが軟腐病とウィルス病ではくさいが減少した。変わって30年後半から40年前半は夏みの早生だいこんとなった。
このだいこんも瘡痂病発生で40年(1965)後半には不安定となった。そこで、次の野菜と云うことで、キャベツの導入を図ったが、秋冬キャベツは年により価格差が大きいので、農家も大いに迷った。
そこに48年(1973)生産農家の負担なしで東京都との契約による価格補償が行われ安値の心配も軽減された。たまたま異常安値に遭遇したが都より補給金が支給され、農家も価格補償制度の必要性を痛感し、54年(1979)から国の価格補償事業にも加入することになった。
現在の栽培は10月~11月出しキャベツが主体で約134㌶が作付けされ、系統共販で、約30万ケースが京浜市場に出荷されている。54年(1979)野菜指定産地(冬キャベツ)に指定された。
2.技術と経営の特色
関宿町の秋冬キャベツは10月を最盛期に11月迄の約2カ月に出荷が行われる。主にトマト・いんげん等の夏果菜の後作として栽培されている。
| 品種 | 9月下~10月出し「早生秋宝」「将軍」「秋徳」 10月下~11月出し「秋徳」「湖月」「YR錦秋」 最近、新キャベツと称して、春系のキャベツの 年内どりで「金春」が増加している。 |
|---|---|
| 播種期 | 10月出しは7月上中旬蒔き、 11~12月出しは7月下旬蒔き、 春系のものは7月下旬~8月上旬蒔きが多い。 |
| 育苗 | 25連結ポットに、練った土を入れて移植する。 育苗日数は30日前後の若苗を植える。 |
| 肥料 | 若苗と果菜類の後作のために肥料は少なく、 化成肥料(15,15,15)で3~5袋程度である。 最近の傾向としては、春系の年内出しの作付けが増加している。 |
ほうれん草(品質のよい野田市のほうれん草)
1.産地のおいたちとあらまし
野田市は利根川と江戸川に囲まれる洪積層火山灰土壌の台地で、ほうれん草は主に秋冬作を中心に栽培されている栽培は個人的にはかなり古くから行われていたが、本格的に産地化されたのは、昭和30年代後半からである。
当時は9月上旬に種を蒔き、年内から1月頃迄の収穫は「豊葉」が殆んどであったが、10月蒔き2月以降の出荷の栽培も行われるようになり、これには「ミンスターランド」が用いられる。
現在の作付面積は、秋冬どりで140㌶、その出荷量は2,100㌧に達している。主な出荷組織として、県北農協予冷部会・旭出荷組合・○谷出荷組合など計35組合が数えられ東京市場を中心に出荷している。秋冬どりの場合、昭和52年(1977)からマルチトンネル栽培技術を導入した。
従来のばら蒔き栽培に比較して、生育も良く収穫時の荷作り調整が能率的なために、市内全域に普及した。今後更に経営を安定させるために、夏どりほうれん草のパイプハウス栽培と、予冷出荷の拡大に意欲的に取り組んでいる。
2.技術と経営の特色
前作はえだまめでその後作としてほうれん草が作付される。夏秋作のほうれん草は、苗立枯病の多発期にあるので、雑草防除を兼ねて植付期に臭化メチル剤で土壌消毒をする。
また、地力を高めるために、完熟堆肥、鶏糞、なたね油粕等、有機質肥料の腐熟したものの利用に努める。
夏蒔きほうれん草のマルチ資材は白黒ダブルマルチの利用が良い。機械蒔きの条間は18~20cm、株間は8~10cm程度、播種量は10a当り4~5㍑(丸粒)で1穴当り5~8粒程度にする。
10月蒔きではべと病が発生しやすい時期で対病性品種が出ているが、従来強いとされていた「パレード」「アトラス」等が発病するようになったので、「ソロモン」を用いるようになった。
11月蒔きの冬の作期では、省力とトンネル内を適温にするため、換気フィルムを使うようにしている。
みょうがたけ(冬の換金野菜野田のみょうがたけ)
1.産地のおいたちとあらまし
昭和30年代までは京浜市場の80%以上を占めていた野田市の「みょうがたけ」は、昭和6年(1931)、野田市中里、石川孫次郎の導入によって始まった。当時、石川孫次郎は埼玉県川口市赤山、田中清太郎から根株30束を譲り受け、秘伝とされていた軟化技術も一緒に作業させてもらって取得したという。
2~3年後周囲の農家数戸が始め、この地から市内の五木新田・岩名へと広まり、更にこの地域からは親戚を通じて市内全域に栽培されるようになった。昭和35年(1960)市内に点在するみょうが栽培農家により組織した○野促成組合を結成し、初代組合長に中島三郎が就任、みょうがの規格統一、花蕾の共販共計、更には、にらの共販共計迄実施した。
野田市のみょうがの出荷組織は○野促成組合の外に2組合がある。
○野促成組合も発足当時は56名の組合であったが、この地域も農地の宅地化が進み、年々栽培面積が減少し、全盛期には100戸以上で30㌶以上もあったが、現在は約30人で10㌶前後となっている。
現在の栽培農家は市内でみょうがの栽培が行われなかった畑を求めて、充実した根株養成と、品質の良い野田みょうがの生産に懸命である。
昭和44年(1969)、野菜振興産地育成事業による集出荷所の建替えが行われた。
2.技術と経営の特色
みょうがの根株養成は比較的粗放であるが、軟化栽培は技術的にも労力的にも集約である。春3月下旬に根株を植え付けると、9月の花蕾、収穫迄は余り労力を必要としない。
伏せこみは茎葉が霜枯れを起す12月から始まり、順次3月まで行われる。
伏せこみ床の大きさは10㎡(2m×5m)程度のものが多く、深さは1.5m程度である。収穫は伏せこみ後60~70日で収穫になるので、冬の農閑期を効率的に利用できる。特殊な野菜だけに品質による価格差は大きい。
この品質では特に「紅」の良否が最も影響する。この「紅つけ」の方法は伏せこみ後20日前後で発芽が揃った時に、軟化床の一部を開放して外気を入れて温度を下げる。
朝8時頃から5~6時間光線を入れ、空気を入れ替える。2回目からは10日後に1回目と同じ方法で行う。
農家では「日入れ」とも云うが、高温(25℃以上)では紅つきは悪いことはわかっていても、当日の天候、醸熱物の温度などに左右されるため、ベテラン農家でも、この「紅つけ」には苦労している。収量は3.3㎡当り150~200束、1箱32束入りで出荷する。